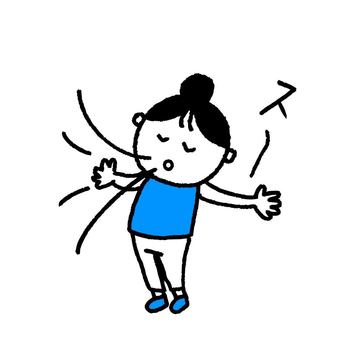10月号 暮らしに役立つ健康ニュース「からだから」
コラム
秋の深まりを感じるこの季節は、朝晩と日中の寒暖差が大きく、体調を崩しやすい時期です。気温が下がることで「冷え」による不調が起こりやすくなり、免疫力も落ちて風邪や感染症にかかりやすくなると言われています。
これから冬に向けて元気に過ごすために、日々の生活の中でできる簡単な冷え対策と免疫力アップの工夫をご紹介します
今月の健康ヒント「冷えと免疫力」
冷えが招く体の不調
体が冷えると血流が悪くなり、肩こりや腰痛、関節痛などの原因になるほか、内臓の働きも弱まり、免疫力の低下にもつながります。
◎冷えを防ぐ生活習慣
- 衣服の工夫:首・手首・足首を冷やさないことが大切です。スカーフや靴下などで調整しましょう。
- 温かい食事:根菜類(にんじん、ごぼう、かぼちゃなど)や生姜を使った料理は体を内側から温めます。
- 軽い運動:ウォーキングやストレッチなど、毎日の軽い運動が血流を促進します。
- 入浴習慣:シャワーだけでなく、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで体が芯から温まります。
◎免疫力を高める工夫
- 十分な睡眠:睡眠不足は免疫力低下の大きな原因です。
- 腸内環境を整える食事:発酵食品を積極的に取り入れましょう。
- ストレス対策:深呼吸や軽い体操で気持ちをリラックスさせることも大切です。
◎冷えを改善するとどうなる?
体を温めると血流が促進され、筋肉や関節に栄養や酸素が届きやすくなります。その結果、肩こりや腰痛の緩和につながるほか、消化器や腎臓など内臓の働きも活発になります。また、血流改善は白血球の働きを高めるため、免疫力向上にも直結します。つまり、冷えを防ぐことは「不調の予防」と「病気に負けない体づくり」に大きな役割を果たすのです。
◎体を温めるおすすめの食材
食事は体を内側から温める大切な要素です。特に秋から冬にかけては、次のような食材がおすすめです。
・根菜類(にんじん、ごぼう、れんこん、かぼちゃ)
…血流を促し、体を芯から温める
・生姜・ねぎ・にんにく
…発汗作用と抗菌作用で風邪予防にも役立つ
・発酵食品(味噌、納豆、ヨーグルト)
…腸内環境を整え、免疫力を高める
・魚介類や良質なタンパク質(鮭、鶏肉、大豆)
…代謝を高め、体温維持に必要
食事・運動・入浴といった日常の小さな工夫が、冬を元気に過ごすための土台になります。
今月の身体の話「秋の乾燥と呼吸器のケア」
秋は空気が乾燥し始め、のどや鼻、気管支など呼吸器系の不調が出やすくなる季節です。乾燥は粘膜のバリア機能を弱め、ウイルスや細菌が侵入しやすい状態をつくります。そのため、秋の健康管理には「潤いを保つこと」が大切です。
◎生活習慣でできる工夫
- 加湿:加湿器や濡れタオルを利用して、室内の湿度を50〜60%に保ちましょう。
- 水分補給:涼しくなると水分摂取が減りがちですが、常温の水やお茶をこまめに飲むことが大切です。
- 呼吸法:深くゆっくり鼻呼吸を意識すると、気道が潤い免疫機能が保たれやすくなります。
◎おすすめの食べ物
梨やれんこん、はちみつは、のどを潤す働きが
あるとされ、秋の食卓にぴったりです。
旬の食材を取り入れることで、自然と体調管理につながります。
10月は「秋の夜長」と言われるように、日が短く夜が長くなります。この時期にしっかり休養を取ることは、心身の回復や免疫力の維持にとても重要です。
◎質の良い睡眠のために
- 寝る前の習慣:スマホやテレビの光は脳を覚醒させるため、寝る30分前からは控えましょう。
- 就寝環境:寝室の温度は20℃前後、湿度は50%程度が理想です。布団や毛布で「寒すぎず暑すぎず」を意識しましょう。
- 夕方以降のカフェインを控える:コーヒーや緑茶は交感神経を刺激し、眠りを浅くすることがあります。
◎睡眠と身体の関係
深い眠りの中で分泌される「成長ホルモン」は、筋肉や皮膚の修復を助け、疲労回復を促します。また、免疫細胞の働きも活発になり、風邪や感染症への抵抗力が高まります。
秋の夜長をうまく利用して、心と体をリセットしましょう。
●なる治療院からのお知らせ●
□トレーニングやリハビリ動作は可能なの?
□鍼灸治療院ってどんな施術をしてくれるの? 等々
気軽に体験して頂ける無料体験施術を行っております!
お一人様(施術25分+問診等のお時間含めて)1時間程度です!